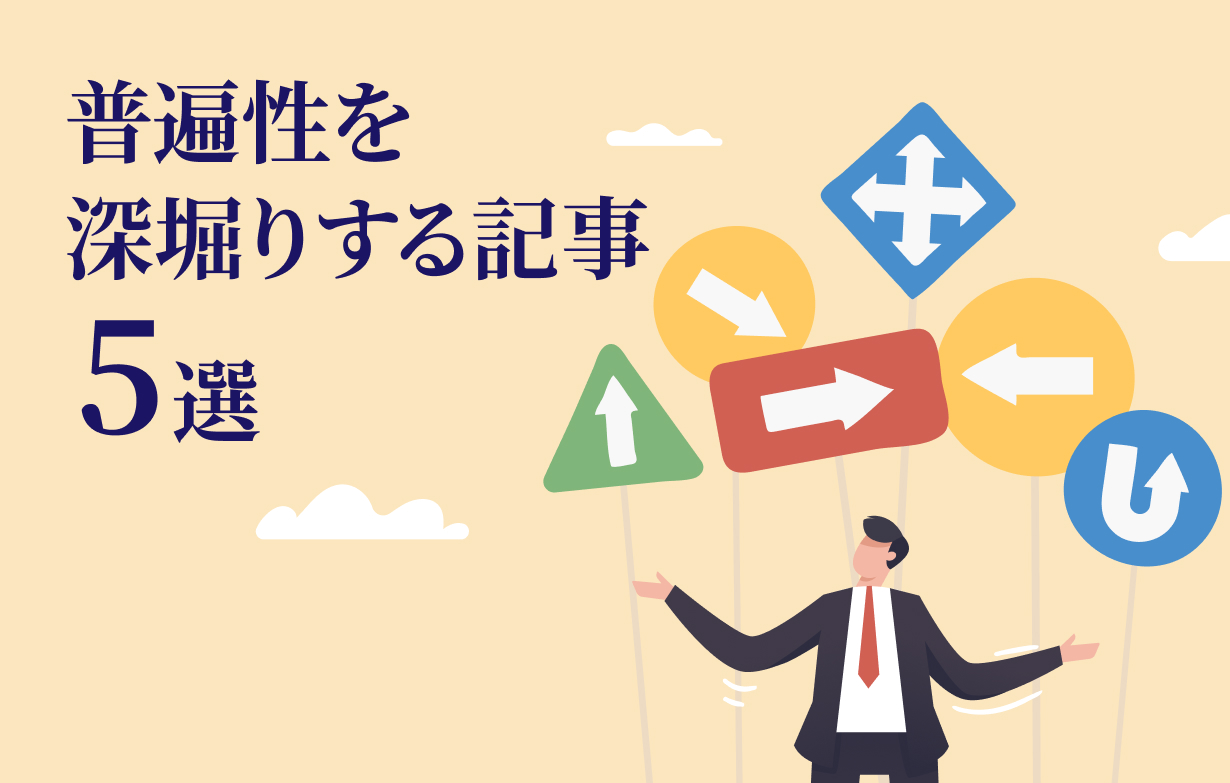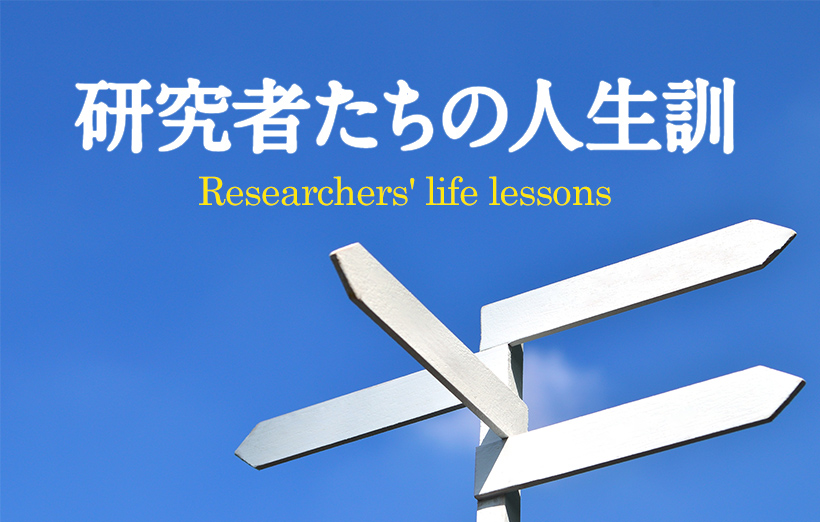「正しい」とは何か?哲学の研究者に聞いた、問うということ|当たり前を考える #4
SNSでの“他人たたき”など、過剰なまでに「正しさ」が主張される現代ですが、そもそも「正しさ」とは何なのでしょうか。普段は深く考えることの少ない基本的な物事について専門家の視点や知見に触れる、「当たり前を考える」シリーズ第4回は、哲学の研究者・久米暁先生と、「正しさ」について考えてみました。

Profile
久米 暁(KUME Akira)
関西学院大学文学部文化歴史学科教授。1998年京都大学大学院文学研究科博士後期課程研究指導認定退学。2001年博士(文学)取得。2003年から関西学院大学へ。研究分野は認識論・言語哲学・メタ倫理学など。特に、デイヴィッド・ヒュームについて深い関心を持ち、研究を進めている。著書に『ヒュームの懐疑論』(岩波書店)など。
この記事の要約
- 「本当にそうなのか」「どうしてそう言えるのか」と問うことが重要。
- 人は揺るぎない真理に到達することは難しいが、だからといって何でもよいというわけではない。
- “仮の道徳”で今を生きながら、同時に問い続ける姿勢が大切。
哲学研究者は世の中をどのように見ているか
——先生が研究されている認識論、言語哲学、メタ倫理学とは、どのような学問なのか教えてください。
簡単にいうと、人はどれだけ本当のことを知ることができるのか、どのように認識ができるのかを研究するのが「認識論」、人は何を語ることができるのか、本当のことをどのように言うことができるのかを研究するのが「言語哲学」です。たとえば、誰かが「○○は△△だ」と話したとします。それを聞いて、もし自分が納得できないとき、「どうしてそうだとわかるのか?」「なぜそんなことが言えるのか?」という疑問を持ちますよね。前者を突き詰めて問うのが認識論、後者の問いを追究するのが言語哲学といえます。
そして、良い・悪い、正しい・正しくないなど、倫理的なものに特化して、認識論や言語哲学を行うのが「メタ倫理学」。人間はいとも簡単に「こうするのが正しい・正しくない」などと言いますが、一歩引いてみて、はたして本当にそんなことがわかるのか?どうしてそう言えるのかを研究するのがメタ倫理学です。私は認識論や言語哲学の研究の一環としてメタ倫理学にも興味をもっています。
——具体的には、どのようなものが研究対象になるのでしょうか。
良い・悪い、正しい・正しくないだけでなく、目に見える事実や科学的なことについても反省して、検討してみようというのが私の研究です。たとえば、ここに青色の表紙の本があったとします。なぜ表紙が青いと言えるのでしょう? 「見たら青いとわかる」と思うかもしれませんが、何も見えない暗闇の中ではどうでしょう。表紙はもちろん、すべてのものが何色かわからなくなりますよね。見る条件によって色は変わるのです。ではどの条件で見えた色が本当の色だといえるのでしょうか。はたまた、生まれ育った国によって、青と緑の区別が自分とは異なるかもしれません。
これは、温かい・冷たいといった感覚も同じで、温かいものでも、触る手の冷たさによって感じ方が変わります。ものごとの捉え方というのは、人や条件によってずいぶん異なる可能性があるのです。そうなると、正しい・正しくないだけでなく、私たち人の認識には、そういう不確かさがつきものなのではと思えてきます。
では、人間の知覚に頼らない場合はどうなるでしょうか。物質を構成するのが素粒子で……などという自然科学的な分野なら、誰もが納得する客観的な説明ができるかもしれません。ですが、今度は「目に見えない素粒子が、本当に存在しているのか」という別の疑問が沸いてきます。自然科学の理論は客観的とされていても、人が見ることがまったくできないものが存在するという限り、「本当にそうなのか?」という問題がつきまとうのです。
実際、揺るがないと思われていたニュートンの古典物理学でさえ限界が見つかっています。科学のあり方がガラッと変わる「科学革命」が何度も起こってきたと言われ、今後もそうかもしれません。そうなると、正しい・正しくないだけでなく、どんな事柄についても「本当にそうなのか」「どうしてそう言えるのか」と問うてしかるべきだと考えています。
哲学的にものを考えることの必要性
——哲学はどんな時代に特に必要とされてきたのですか。
哲学は学問の中で最も歴史がありますが、3000年~4000年前から「問うこと」を伴っていました。ソクラテスやプラトンたちが世界のあり方や正しい生き方などを話すと同時に、「なぜ、そう言えるのか」と問う、今でいう反省が行われるのです。そんな哲学がクローズアップされる時代が何度かありました。それは、人が世界についての認識をガラッと変えるときです。
——人が認識を変えるのはどんなときですか。
もっとも大きく変わったのは、16世紀から17世紀です。数学を用いた自然科学研究が行われ、人類の歴史を大きく変えた時期にあたります。新しいタイプの学問が台頭してくると、「なぜそれがわかるのか」と、認識論が強く探究されるようになったのです。同じ頃、西洋は大航海時代の真っ只中にあり、アジアやアメリカ大陸で自分たちとは異なる文化を発見。また、宗教革命によって、カトリック教会からプロテスタントが分離されました。
こうなると、自分たちが正しいと思っているものは一つではなく、いろいろな可能性がありうると気づく。いろいろな科学や文化、宗教の可能性を発見することで、常識に頼ってはいられなくなり、「どちらが正しいのか」「どうしてそう言えるのか」という問いが生まれるのです。そして、これまで正しいと思われていたことでも、あまり客観性がないと判断されたり、新しい考え方が採用されたりと人も社会も変わっていきます。
——新しい科学技術が次々と生まれている今、「正しさ」も変わるでしょうか。
現代においては、新しい科学技術がどんどん登場していて、どうしたらよいか常識でははかれないことに直面しています。生成AIで論文やリポートを書くのはよいのか? クローン技術はどこまで使ってよいのか? 新しい技術が出てくると、どう使えばよいかがすぐに問題になりますが、その答えはまだありません。
今問題になっている自動運転について考えてみましょう。自動運転では、適切な判断を下せるように正しい答えを事前に学習させておく必要があります。たとえば、5人の子どもが飛び出してきたけれど、子どもたちを避けるためにハンドルを切ると別の人に当たってしまうという場合、どうするのが正しいのか? 似たような状況は頻繁に出てくると考えられるので、どう判断するかをAIに組み込まないといけません。直感的にわからないこと、今まで考えたことのない倫理的な問題が出てきています。
“仮の道徳”を持ちつつ、同時に問い続けること
——問いに答えはあるのでしょうか。
正しい・正しくないということだけでなく、科学を含めて、どんなことに関しても人は絶対的な客観性、つまり揺るがない真理に至るのは難しいことだと考えています。一方で、絶対的な客観性が得られないからといって、「何でもよい」というわけでもないと思います。絶対的な客観性とも完全な主観性とも違う、“中間の道”が重要です。完全な客観性があるという絶対主義を主張する人もいれば、完全な主観性しかないという相対主義を主張する人もいますが、私はそれの“中間の道”を歩き続けたいのです。
実は、絶対主義も相対主義も、どこかで立ち止まっていい、と私たちに告げます。客観的な答えに行き着くことができればそれに安住すればよいし、そもそもどれでもよいのであれば好きなものを選んでそれに固執すればよい、というわけです。でも、“中間の道”は、相対主義に対しては、固執せずにもっとよいものをめざしていこう、と言うし、絶対主義に対しては、客観的に正しいと思えても、もしかしたら間違っているかもしれないと考えて、探求を続けていこう、と言うのです。つまり、“中間の道”とは、どこかで停まることなくどこまでも探求を続けるという道です。
——答えの出ない問いを常に考えて生きるのはつらくないでしょうか。
「我思う、故に我あり」という言葉で知られるデカルトは、常識や先入観をすべて疑う「方法的懐疑」という手法によって、世の中はすべて嘘や間違いとしたうえで本当に正しいものを考えようとしました。すべてを疑い、すべてを確かめるのは膨大な作業になり、実際には難しいでしょう。しかし、人は何も信じずに生きていくこともできません。
そこで、デカルトは“仮の道徳”という考え方を提唱しました。今あるものを当座のもの、仮のものとして受け入れることが重要だとしたのです。“仮の道徳”で生きていくと同時に、本当のことを知る努力を続ける。この二本立てでなければ、人は哲学的に生きていくことはできないと考えました。ただすべてを疑うだけではニヒリズム(※)になってしまって、何も進まず、人として生きていけません。あくまで仮という意識を持ちながら、一方で探究し続けること。私自身も“仮の道徳“で生きています。
※虚無主義。あらゆる事象や物事の根底に虚無を見いだし、すべて無価値とする哲学上の世界観。
今、新しい科学技術や考え方が出てきていて、ついていけないこと、受け入れにくいこともあるでしょう。そんなときには、時代がもとめるものを“仮の道徳”として捉えて生きていく一方で、その受け入れにくさや居心地の悪さを大切にして、「本当にそれでいいのか」と考え続けたいと思っています。
——考えることを止めないという姿勢が大切なのですね。
哲学は英語でフィロソフィー(philosophy)といいますが、古代ギリシア語のフィロソフィアが由来で、愛するという意味のフィロス(philos)と知識を表すソフィア(sophia)からできています。哲学には、誕生当初から、人が絶対的な知識や究極的な答えを獲得して終わることはないという反省がありました。人にできるのは知識を愛し続けること、希求し続けること。無理かもしれないけれど追い求める態度がフィロソフィアです。考えて出した答えがあったとしても、それは当座のもの、仮のものだと自覚し、本当にそうなのかと問い続ける態度が大切です。その態度そのものが今の私たちに必要なものではないでしょうか。
取材対象:久米 暁(関西学院大学文学部文化歴史学科 教授)
ライター:ほんま あき
運営元:関西学院 広報部
※掲載内容は取材当時のものとなります