
カミュが描いた“世界”との関わりから、幸福のあり方を考える
1957年に当時史上2番目の若さでノーベル文学賞を受賞したフランスの作家、アルベール・カミュ。不条理を描いた『異邦人』をはじめ、『ペスト』、戯曲『カリギュラ』などで知られ、数年前には70年ぶりに『ペスト』の新訳が出るなど、その作品は今なお注目されています。高校2年生のときに『異邦人』と出会って衝撃を受け、カミュの研究者になったという東浦弘樹先生に、カミュが描こうとした世界観をお聞きするとともに、カミュをはじめとする文学作品が現代の私たちに与える価値についてお聞きしました。
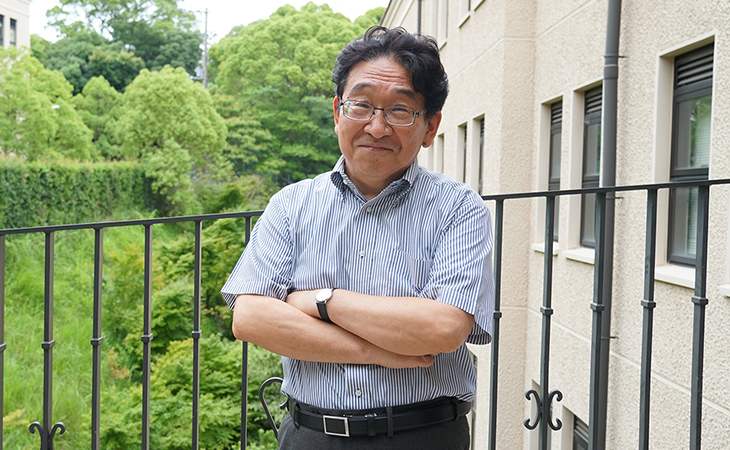
Profile
東浦 弘樹(TOURA Hiroki)
関西学院大学文学部文学言語学科教授。フランスのピカルディー・ジュール・ヴェルヌ大学で博士号(文学)取得。1991年に関西学院大学に着任し、2002年4月から現職。20世紀フランスの小説と戯曲、とくにアルベール・カミュの作品を研究している。また、演劇ユニット「チーム銀河」の代表であり、劇作家・役者としても活動。著書に『晴れた日には『異邦人』を読もう―アルベール・カミュと「やさしい無関心」』『フランス恋愛文学をたのしむ―その誕生から現在まで』(いずれも世界思想社)など。
この記事の要約
- 不条理と訳されるフランス語l’absurdeは、日常的に使われる言葉。
- カミュのいう不条理とは、人間の問いに世界は答えないという状況。
- カミュは『幸福な死』『カリギュラ』『異邦人』『シーシュポスの神話』において、世界との関わり方を4パターン提示した。
- 『異邦人』『ペスト』『転落』を読めばカミュの考えとその変遷がわかる。
不条理とは、人間の問いに世界が答えない状況
災害やコロナ禍で『ペスト』が再注目されたアルベール・カミュですが、やはり代表作といえば『異邦人』(原題はL’Étranger)。推薦図書にしている学校もあり、学生のころに読んだ人も多いことでしょう。読んでいなくても、『異邦人』というタイトルや冒頭の「きょう、ママンが死んだ」という文章に聞き覚えがあるかもしれません。
『異邦人』の主人公、ムルソーは母の死を悲しむことなく、葬儀翌日に恋人と海ではしゃぎ、数日後にアラブ人を射殺。その理由を「太陽のせい」と答えます。そして、死刑を宣告されますが、ムルソーは「僕は幸福だったし今もそうだ」と感じるのです。
カミュは『異邦人』で〈不条理〉を描いたといわれています。〈異邦人〉や〈不条理〉という言葉から、哲学的で難解なイメージを抱く人もいるかもしれませんが、東浦先生によると、どちらもフランスでは日常的に使われる言葉。〈異邦人〉(l’étranger)は「外国」や「外国人」や「よそ者」「見知らぬ人」、そして〈不条理〉(l’absurde)は「ばかげたこと」や「理屈に合わないこと」を意味します。
「不条理はフランス語でabsurde、英語なら absurd。『そんなアホな』『ばかげているよ』という意味です。ごく普通の単語をカミュは使っているんです。ただ翻訳する際に『そんなアホな』とするわけにもいかず、〈不条理〉という和訳が定着したのだと思います。このように、普通の言葉なのに〈異邦人〉や〈不条理〉と訳すと、堅苦しい印象がついてしまう。だからこそ、逆に日本人にはウケたのかもしれません」
では、カミュのいう不条理とは何でしょう。
「悲しいことや辛いことがあったとき、人間は『なぜなんだ!?』と問います。理由がわかったところで現実は変わらないとはいえ、それでも問う。意味や理由がわかれば耐えられるけれど、人間は意味のない苦しみには耐えられないからです。日本人なら神や天に向かって問うというところを、神も運命も信じていなかったカミュは世界に向けて問いを発します。でも、世界は答えてくれない。辛いですよね。人間の問いに世界は答えないという状況が、カミュのいう〈不条理〉なのです」
貧困や母親の沈黙と無関心が作品に影響
ところで、カミュはどういう人物だったのでしょうか。カミュは1913年、当時フランス領だったアルジェリアに生まれ、翌年に父親が第一次世界大戦で戦死したため、母親の実家で暮らしていました。その暮らしは決して豊かではなかったと東浦先生は言います。
「カミュは貧しかったけれども、『貧困は決して私にとって不幸ではなかった』と後年、述べています。カミュは自然という言葉を使わず、自然のことを世界と表現するのが特徴なのですが、一歩外に出ればそこには世界の美しさがあった、そして世界とひとつになる喜びがカミュの少年期を照らしていたからです」
また、カミュの作品を考えるとき、この少年期の貧困に加えて母親の存在が大きなポイントになると言います。
「カミュの母親は無口で、何ごとにも、息子であるカミュに対してさえも無関心でした。そして、字を読むことができませんでした。作家の母親が字を読めないとはどういうことか考えてみてください。カミュがどれだけすばらしい作品を書いても、のちにノーベル文学賞を取っても、母親に読んでもらえないのです。カミュの少年期を占めているのは母親の沈黙と無関心でした」
世界とひとつになる喜びや母親の沈黙と無関心は、彼の生涯のテーマになったと東浦先生は指摘します。このほか、17歳のときに結核で死の淵をさまよったり、第二次世界大戦時ナチス・ドイツに対するレジスタンス運動に参加したことから、カミュの作品には常に死の影が漂い、〈反抗〉や〈連帯〉が描かれたりしているそうです。
世界との関わり方、幸福のあり方はいろいろ
幸福の追求という観点からカミュの作品を研究している東浦先生。「世界とひとつになることは喜びであり、逆に世界から引き離されることは不幸」という解釈をしています。いわゆる「不条理の三部作」とされる、『異邦人』『シーシュポスの神話』『カリギュラ』、さらに『異邦人』の前身となる小説『幸福な死』(※)を合わせた4作において、カミュはどのように喜び、つまり幸福と、そこにつながる世界を捉えているのでしょうか。
※カミュは生前『幸福な死』を出版しなかったが、死後に出版され、今では日本語訳も出版されている。
「これら4作を読み込むと、世界と人間の関係について、作品同士がシンメトリーを描くようにつくられていることがわかります。『幸福な死』の主人公のメルソーは、自分が幸福になるために、裕福な男性を殺して金を奪います。メルソーのイメージする幸福とは小石になること、小石になって雨が降れば雨に濡れ、太陽が照る日は熱くなる、すべての流れのままにあることが幸福だとメルソーは捉えました。世界の一部になる、世界に飲み込まれること、考えようによっては胎内回帰願望といえるかもしれません。小石となって何も考えず、世界の一部になれば、何の苦しみもなく幸せだとメルソーは考えるのです。一方、『カリギュラ』では、メルソーとは逆に自分が世界を飲み込もうとします」
ローマ皇帝カリギュラは、妹であり愛人でもあったドリジュラの死後、「神々と肩を並べる存在になる」と言い、無作為に死刑を行うなど残虐行為を繰り返します。それは神々が行っていることと同じであり、神々の行いを受け入れるなら、自分の行いも受け入れるべきだというのがカリギュラの言い分です。では、『異邦人』のムルソーはどうでしょうか。
「ムルソーは独房で『僕は世界のやさしい無関心にはじめて心を開いた』と言います。世界を『自分とよく似たもの、兄弟のようなもの』と感じる。つまり、ムルソーは世界と対等のままひとつになるのです。一方で、『シーシュポスの神話』では、人間の問いに世界は答えないという不条理な状況、世界と人間との対立関係は解消されません」
シーシュポスはギリシア神話の登場人物で、神々から最も重い刑に処されています。それは、巨大な岩を山頂まで運ぶこと。ですが、やっと山頂に着いたら岩は谷底まで転がり落ちてしまい、シーシュポスはこの無意味な作業を永遠に繰り返さなければならないのです。
「でも、カミュはその状況から目を背けずに見続けることでシーシュポスは幸福になれる、『シーシュポスは幸福だと想像しなければならない』と締めくくります。つまり、世界と人間は対立しているが、対立を解消するのではなく、対立を対立のまま保つことこそが幸福なのだというのです」
世界が人間を飲み込む『幸福な死』、人間が世界を飲み込もうとする『カリギュラ』、対等のまま世界とひとつになる『異邦人』、世界と人間が対立したままの関係である『シーシュポスの神話』。世界と一体になるあり方、つまり幸福のあり方もいろいろあると、これらの作品から知ることができます。
文学作品は人間の真の姿を見せてくれるもの
カミュは不条理ばかりをテーマにしていたわけではありません。『異邦人』を含む「不条理の連作」のあと、『ペスト』や『反抗的人間』などからなる「反抗の連作」を発表し、さらに「愛の連作」になるはずだった『最初の人間』の執筆半ばに交通事故で亡くなりました。東浦先生は、『異邦人』『ペスト』『転落』の3作を読めば、カミュの考えとその変遷がわかると話します。『ペスト』は文字通り疫病に襲われた街の様子を描いた小説で、『転落』は順風満帆だった男がその幸せを失う話です。
「『ペスト』には、医師のリウーと彼を手伝うタルーが、友情の記念にと海で泳ぐ印象的なシーンがあります。毎日たくさんの人が死んでいくペストとの闘いの中で、ほんの一瞬の安らぎがある。そのとき、2人はものすごい幸福感に包まれます。『転落』の主人公クラマンスは、パリで弁護士の職を失ってアムステルダムにたどり着き、過去の罪を告白するものの、それでも最後に『私は幸福だ、私が幸福でないと思うことを禁じます』と言います。もちろん、逆説的な表現でクラマンスは幸福であることを夢見ているんです。結局、どの作品もすべて幸福というテーマにたどり着くのだと思います」
幸福や苦難に抗う姿、仲間との連携などを描いているカミュの作品群。複雑化した現代を生きる私たちは、これらの作品から何かヒントを得られるのでしょうか。東浦先生に尋ねると、「文学作品に人生訓や生きるためのヒントを求めることは好ましいことではないと、私は思っていますが」と断った上で、文学の魅力についてこう話してくれました。
「文学作品は人間の真の姿、その愚かしさと美しさ、栄光と悲惨を見せてくれるものです。文学作品を読むことには未知のことを知る喜びと既知のものを知る喜びがあります。作品を読むことで、私たちは自分とは違う価値観や生き方を知ることができると同時に、自分自身の経験に意味や価値を与えることができるのではないでしょうか」
この先生のコラムを読む
取材対象:東浦 弘樹(関西学院大学 文学部文学言語学科 教授)
ライター:ほんま あき
運営元:関西学院 広報部
※掲載内容は取材当時のものとなります







