
現象学から考える、「聞こえないこと」で成立する世界|デフリンピックが私たちに語ること #2
2025年11月15日から26日にかけて「東京2025デフリンピック」が開催されました。日本で初開催のデフリンピックは、私たちに何を語りかけたのでしょう。そこで「月と窓」では、デフリンピックを軸に、3回にわたって特集記事を連載します。2回目の今回は、哲学の分野の一つである現象学を研究する景山洋平先生が登場。「当事者の視点」という現象学のキーワードをもとに、聴覚障がい者のコミュニケーションのあり方について考えます。
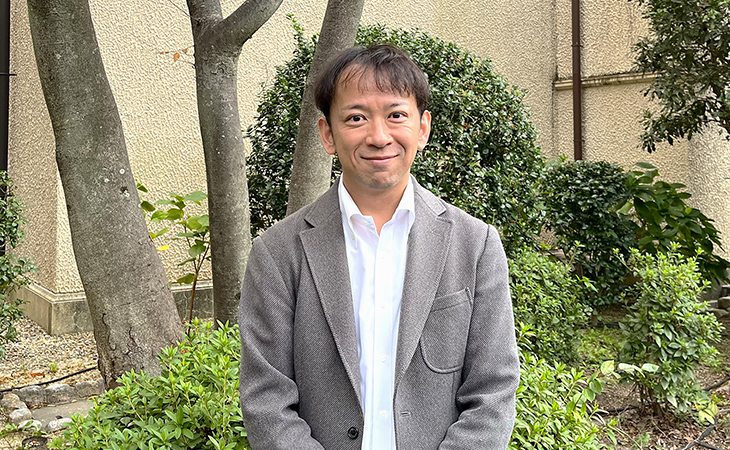
Profile
景山 洋平(KAGEYAMA Yohei)
関西学院大学文学部 教授。東京大学大学院人文科学研究科博士課程修了。博士(文学)。日本学術振興会特別研究員、東京大学専任講師を経て、2019年に関西学院大学に着任、2023年4月より現職。哲学、倫理学を研究分野とし、現在は現象学に主軸を置いて論文執筆や講演活動に取り組んでいる。著書に『「問い」から始まる哲学入門』(光文社、2021年)、『出来事と自己変容:ハイデガー哲学の構造と生成における自己性の問題』(創文社、2015年)などがある。
この記事の要約
- 現象学は、当事者の視点から世界における経験をどう受けとめるかを考察する学問。
- 医療やリハビリの現場でも活用され、患者自身の経験や回復プロセスを捉える一助となる。
- 「聞こえる」「聞こえない」によって、空間認識などにおける身体感覚が根本から異なる。
- デフスポーツによって自分と異なる世界を知ることは、自身の生き方の問い直しにつながる。
当事者の視点を徹底する、現象学が示す世界との向き合い方
現象学は哲学の学派の一つで、20世紀初頭にオーストリアの哲学者であるエトムント・フッサールが、「先入観を捨て、事象そのものと向き合う」という現代まで続く現象学の考え方を確立しました。フッサールの現象学は20世紀以降のヨーロッパ哲学において大きな分岐点となり、現代では心理学や社会学、宗教研究、医療・看護といった分野でも活用されています。
「現在、私が研究している現象学は、当事者の視点から経験されるもののあり方を考える学問です。言い方を変えると、自分に起こっていることに対して、居合わせる自分自身の立ち位置から丁寧に向き合うという考え方です。被験者を第三者として研究する心理学とは対照的に、当事者である自分を研究の軸とすることが大きな特徴です。当事者の視点から、この世界をどのように経験して受け止めるか、または受け止められているかを考察するのですが、それは単に個人的な範疇だけでなく、社会との関係性や自分の身体的状況も大きな要素となってきます」
現象学を考えるうえで重要なキーワードとなる「当事者」の視点は、「身体的状況(身体性)」と「知覚」が密接に関連し、生み出されると景山先生は語ります。
「たとえばここに名刺入れがあったとします。私たちはこれを精巧に印刷された平面ではなく、立体として知覚しています。それはみなさんが今、自分のいる位置から体を動かして、別の側面から名刺入れを見る可能性があることで起きる考え方です。もし、私たちが一つの側面からしか名刺入れを見ることができない身体だとしたら、立体であることを理解できないでしょう。これは日常生活における空間認識とも連動しており、教室の中に一人でいる時と大人数でいる時では、広さや動き回れる範囲が異なって感じられます。この感覚は、まさに自分の置かれている状況である現象と、自分自身の身体的状況がリンクしていることを示しています」
また、フッサールが確立した現象学では、「間主観性」という自身と他者の間で共有される世界や意味も考察を行う上で重要な定義の一つであるとされています。景山先生は間主観性のあり方について、言語によるコミュニケーションだけでなく、アイコンタクトや空気を読むなど、感覚的レベルのやり取りも重要な役割を果たすとしています。
「当事者は自分の視点から自身を取り巻く世界に向かい、関わり合っているので、他者の視点に立つことはできません。しかし、他者もまた本人の視点から自身を取り巻く世界に関わり合っており、それぞれの視点においてこの状況を理解していると思われます。この理解を共有するうえで、視線を交わす行為は間主観性における原初的な経験となります。空気を読むことについては、寒い空気、なごやかな空気、リラックスした空気などが同じ空間にいる人全体で共有され、自分と他者との関係性の中で成り立つ経験となります。これらのコミュニケーションは言葉に置き換えると複雑ですが、身体や感覚を用いることで直接的に感じ取れることが大きな特徴となっています」
医療分野における現象学のあり方をもとに聴覚障がいを捉える
今回のテーマであるデフリンピックや聴覚障がいについて考える前に、医療分野において現象学が果たす役割から、もう少し理解を深めてみましょう。先に述べた通り、現象学は医療・看護の分野でも用いられて、脳卒中や精神疾患のリハビリテーション、認知症のケアにも活用されています。景山先生も作業療法の分野で、現象学の応用の研究を行っています。
「作業療法では、病気やけがで障がいを負った際のリハビリテーションとして、日常生活における動作の回復に重点を置いています。この営みを現象学によって学問として明確化させ、治療に活用したいということで、医療系大学の研究者と共同で研究を行ってきました」
リハビリテーションにおける現象学は、患者にとっての生活上の意味から障がいとの向き合い方を考え、日常生活を取り戻すための助けとなることを役割としています。
「患者の経験世界を捉え、評価するのは作業療法研究の理論的なモデルとなります。まずはこの理論的なモデルを現象学の立場で再検討することから始めました。その次の段階として、患者が障がいを受け入れた『障害受容』の状態で、日常に復帰するまでの心の変化や、セラピストはそこにどう関わるかということを研究テーマとしました。日常が失われ、再構築するプロセスは現象学としても考え得る事柄であり、抽象度の高い哲学のフレームワークから、どのように捉えられるかということをみんなで話し合いました。ただ、『障害受容』は第三者が当事者に押し付けるものではないので、私たちは、あくまで相談相手に徹することを心がけています」
現象学の成り立ちと特徴、そして医療現場での活用例をふまえ、今回のテーマである聴覚障がい者の視点を捉えると、健常者との違いはどのように現れるのか。景山先生は、自身の体験が「聞こえない世界」における間主観性のあり方を考えるきっかけになったと語ります。
「健常者にとっては、自分のいる空間の広さや、建材の違いによって生まれる音の響き方が空間認識に大きな影響を与えます。そのため聞こえる人と聞こえない人では、空間に身を置く際の身体感覚が明らかに変わると思われます。私は以前、手話カフェと呼ばれる飲食店で、お客さんや店員さんが手話、もしくはメニューを指さして注文するという状況を体験したのですが、音声を介さないコミュニケーションが成立する場が想像以上に静かなことに驚きました。こういった場では相手に視線を向けてコミュニケーションを取ることが前提なので店員さんとの距離感が近く、間主観性のあり方も健常者とは根本的に変わってきます」
聴覚障がい者の世界にふれた景山先生は、健常者が「自分は優位な立場である」と無意識のうちに捉え、両者の間に大きな溝を生み出していると考えています。
「聴覚障がい者の感覚を理解する際、私たちは彼らのことを『自分が持っている聴力を持たない人』という尺度で考えがちです。これは、現象学の枠組みが健常者モデルで構築されている部分も要因の一つなのですが、実際の聴覚障がいの感覚を知るには、やはり当事者の言葉こそが重要となってきます。一方で、私たちも聞こえないからこそ広がっている世界があると想像を巡らせることが大切です。このようなプロセスを経ることで、聴覚障がい者と健常者が共に納得できるような考え方が生まれ、より普遍的な現象学が形づくられていくのではないかと思います」
デフスポーツが生み出した応援文化と健常者スポーツとの差異
聴覚障がい者が活躍するデフリンピックでは、選手を応援するために手話をベースとする「サインエール」が開発され、サポーターたちに活用されました。デフスポーツから新たな応援文化が生まれたことで、これまで暗黙のうちに度外視されてきたデフスポーツのサポーターにスポットが当たる機会になりました。
「競技場でたくさんの人たちがサインエールを行い、選手を応援する映像を初めて見たのですが、とても新鮮かつ情熱的な動きに心を動かされました。サインエールと健常者アスリートへの応援を比較してもその熱量に違いはなく、選手たちに活躍してほしいという思いは十分に伝わってきます。先ほどの手話カフェの話にも通じますが、距離感や感覚が健常者と異なる分、より強く応援されていると感じます。集団でのサインエールはすでに新たな応援スタイルとして確立されつつあります。もう数十年、慣習的に使い続ければ伝統文化として受け継がれていくのではないでしょうか」
デフスポーツを鑑賞する中で、景山先生は他のパラスポーツとの違いについても着目し、中でも卓球の特異性には大きな気付きがあったとも言います。
「ボールをラケットで打つ音やテーブルにぶつかる音が聞こえない中、相手の選手がラケットを振っている姿やボールの動きを視覚のみで追いかける。音がない世界であれだけ激しいラリーを繰り返すのが、いかに特殊な状況であるかということは私たちには想像が及ばないところです。健常者スポーツとは明らかに異なる、聴覚障がい者特有のトレーニングの先にあの試合展開があるということに胸が熱くなります」
では、デフスポーツが人々を魅了する背景は、現象学、そして間主観性の観点から、どのように語ることができるのでしょうか。
「まずは、自分にはない世界や経験のあり方に引き込まれる部分があります。一方で、自分とは違う経験をしている人々にふれることで、当事者として生きている経験をあらためて振り返る。この2本の柱がデフスポーツと自分の関係を考えるうえで重要になります。健常者たちは自分と同じように聞こえる人たちと経験世界を組み立てるので、デフスポーツのアスリートが活躍する姿を見て、無意識のうちに聞こえない人を排除・線引きしていることに気づくという意味合いもあると思います」
現象学を通して聴覚障がい者の当事者が見る世界、そしてデフスポーツの魅力にふれてきた景山先生。今後の現象学のあり方については、当事者の視点を持ちながら、幅広く社会と接点を持つことに社会的意義があると強調します。
「自分にとって当たり前のものを受け止め直すうえで、自分とは異なる方法で社会と向き合っている人と関わるのは、とても重要な行動です。自分という存在は、ある程度社会的な広がりを持っているけれど、それ以外の目の前にいる人たちもまた別の世界の当事者です。そう考えると現象学が捉えたい真理の源泉は、当事者の数だけ無数にあるといえるでしょう。その当事者たちと関わり合って、お互いの考えをどのように受け止めるかが最終的には重要となります。それを理解したうえで自分が世界をどう見て、受け止め、経験しているか、存在しているかを問い直す。そうすることで、自分にふさわしい生き方を見つけることができるのではないでしょうか」
取材対象:景山 洋平(関西学院大学 文学部 教授)
ライター:伊東 孝晃
運営元:関西学院 広報部
※掲載内容は取材当時のものとなります






