
日本の離婚事情は世界と違う?「共同親権」導入から考える親の責任と子どもの幸せ
2023年8月、法制審議会の部会で、離婚後も父母双方が子どもの親権を持つ「共同親権」の導入に向けた民法改正案のたたき台が提示されました。これまで離婚後は父母のいずれかが親権を持つ「単独親権」のみだった日本で、「共同親権」が選択できるようになるとどう変わるのか。親権を扱う家族法について、アメリカとの比較研究を進める山口亮子先生にお聞きしました。

Profile
山口 亮子(YAMAGUCHI Ryoko)
関西学院大学法学部教授。博士(法学)。山梨大学助教授、京都産業大学教授などを経て現職。フロリダ大学ロースクールやペンシルベニア大学ロースクールで客員研究員を務める。専門分野は民法の家族法。研究テーマは親権、面会交流、児童虐待防止、ハーグ子奪取条約、児童の権利条約など。また、アメリカの家族法と日本の家族法を比較検討しながら、国家と家族の関係、あるいは国家と親と子どもという三者関係から問題を捉え、個々の課題を検討している。著書に『日米親権法の比較研究』(日本加除出版)など。
この記事の要約
- アメリカでは「養育計画書」を提出しなければ離婚が認められない。
- 世界的には「共同親権」がスタンダード。「単独親権」のみの日本は少数派。
- 両親の関係性によって、親子の関係まで断たれてしまうのが日本の問題点。
離婚後も両親との関係を保つことが、子どもにもいい影響を及ぼす
親権とは、子どもの世話や教育などを行う親の権利と義務のこと。婚姻中であれば、両親が共同で行使する「共同親権」となりますが、日本の場合、離婚後はどちらか一方だけが親権を有する「単独親権」が適用されます。それがあまりにも当たり前になっていますが、「共同親権」が日本で導入されると、どうなるのでしょう。
山口先生が研究するアメリカ各州の法律では、離婚時に「単独親権」と「共同親権」を選べますが、共同親権が選ばれることがほとんど。共同親権の場合、離婚後も変わらず親子の交流が続き、月2回の週末は、離れて住むもう一方の親のもとに泊まりに行くのが一般的なのだそうです。
「アメリカでは、離婚後の子どもの日々の送り迎えをどうするか、病院はどこに連れて行くかなど、離婚前に事細かに決めていきます。長期休暇は普段離れて暮らす親のところで過ごすように約束することが多いようですし、クリスマスや誕生日などの年間行事については、偶数年と奇数年を交代で過ごす…という決め方をするそうです。離婚しても子どもを連れて旅行をするときには相手に通知し、同意を得なければならず、転居も自由にはできません。こういった決め事を、10数ページにわたる『養育計画書』にまとめて裁判所に提出しなければ、そもそも離婚が認められないんです」
さすがは契約社会と呼ばれる国です。もともとアメリカも離婚後は「単独親権」のみでしたが、1980年代に「共同親権」も選択できるようになりました。「養育計画書」は1989年にワシントン州で始まり、一気に広がっていったそうです。
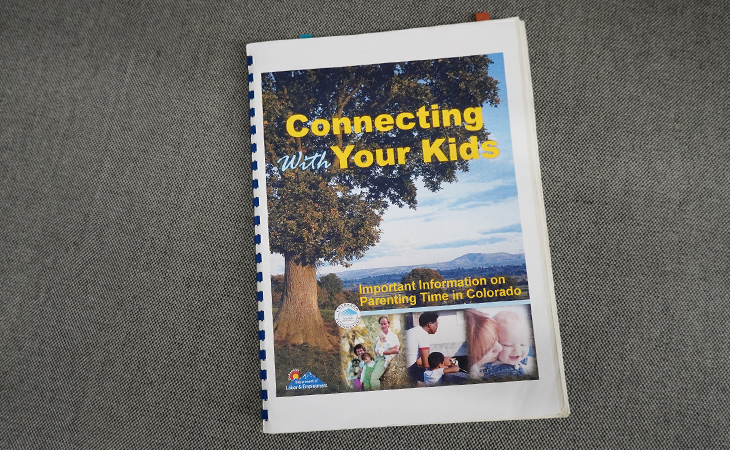
「細かな内容は州によって違いますが、この『養育計画書』のガイドラインには、年齢ごとの子どもの心理状態や必要なこと、共同で面倒を見ることの重要性なども書かれていて、父母ともに勉強する必要があります。冊子にまとめられていても、なかなか自分たちだけで決めるのは難しいので、弁護士やファミリー・コーディネーターを雇うことも珍しくありません。時間とお金と労力はかかりますが、ここまで準備しないと離婚してはいけないというのが社会的なルール。そうしないと、子どもに不利益が生じると考えられているわけです」
なるほど、離婚するのも一苦労です。しかし「共同親権」によって行動が細かく決められ、両親のもとを行き来するのは、子ども自身が嫌がるということはないのでしょうか。
「『嫌がる』というのは、日本的な考えかもしれません。アメリカでは衣類も双方の家それぞれに置いておくなど、離婚しても自由に会える状態を整えています。海外の調査では、離婚後も両親との関係を保つことが、子どもの精神面にも成長にもいい影響を及ぼすという研究結果が数多く出されています。しかし『単独親権』しか行使できない日本では、その研究も進んでいないのです」
離婚後、無条件に「単独親権」となる日本は少数派
アメリカだけでなく、離婚後の親権は「共同親権」が世界的にスタンダード。無条件に「単独親権」しか選択できない日本は少数派です。「長年の間、日本はガラパゴス化していた」と山口先生は指摘します。
「アメリカでは40年以上も前からですが、ヨーロッパでも30、40年前には『共同親権』を取り入れています。日本では通常、親権を喪失させるためには非常に厳しい要件があり、裁判も必要で時間がかかります。しかし、いざ離婚となれば、なんの落ち度がなくとも、一方の親権が簡単に失われてしまいます。けれど日本では『単独親権』が当たり前になっていて、長らく疑問視もされていませんでした」
ここで少し、日本の親権事情をひも解いてみましょう。日本の民法には「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う」(第820条)とだけ書かれています。これはなんと、1898年に公布された明治民法から125年以上も変わらず、2011年の改正で「子の利益のために」という言葉が加えられただけだそうです。
「明治民法は『家制度』で、父親が決めた結婚、職業に異を唱えられず、相続も長男だけに権利がある、非常に偏ったものでした。それが戦後、日本国憲法と同じ1947年に公布された新しい民法で、人権に関わる家族法だけが大きく改正されました。しかし家族法のうち親権については変わらず、2011年までの民法では、『懲戒場に入れることができる』という文言が残されており、『親権を行う者は(中略)監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる』と、子どもを『懲戒』する権利が認められていたのです」
民法上で「懲戒とは何か」とまでは規定されていなかったものの、親が子を「懲戒できる」と表現されていたとは、知らない者からすると衝撃的な話。この言葉は、なんと2022年末まで記されていたといいます。
「2022年12月の改正で、親権を行う者は、子どもの年齢・発達への配慮、体罰の禁止、健全な発達を阻害しないといったことが、新たに記載されました。体罰を禁ずるだけではなく、健やかに育てることまでうたわれたのは、大きな飛躍です。しかしこの民法改正の流れからも、日本の歩みの遅さをうかがい知ることができるでしょう」
欧米の「共同親権」導入は、養育費確保の目的も
結婚を選ばず子どもを生み、育てている人たちの割合は、フランスで60%近く。アメリカで約40%存在しますが、日本にはわずか2%しかいないのだとか。このデータの背景として、海外では事実婚の関係でも親権は両親にありますが、日本は婚姻関係を結ばなければ両親ともに親権を持つことができない法制度が大きく関係していると山口先生は分析します。

そして現在の日本では、離婚後は80%以上が母親の「単独親権」に。「明治時代は婚姻中も離婚後も父親だけに親権があり、戦後も父親が親権を持つ割合が高かったのですが、高度経済成長期になると、“夫は仕事、妻は家庭”といった性別による役割分担のイメージが一般化。それにより母親が親権者になる割合が上がっていった」と山口先生は説明します。
「日本では離婚後に親子の交流が途絶え、親権を持たないほうの親が子どもに会うのは月1回が30%程度、養育費の支払いは30%に満たないのが現状です。このデータからも、日本には親権者でなくなると、子どもに関係しなくていいと考える人が少なくないともいえます」
離婚後に親権を持たなくなった男性の多くが養育費を支払っていないというのは大変な事態です。「それがまかり通るぐらい、日本は母子家庭に対する公的支援が手厚いともいえます。アメリカでは『共同親権』が制定されるとともに、養育費履行強制制度も確立しました。それまでは、養育費を払わずに支援に頼る“逃げおおせた者勝ち”に対しては、納税者の怒りが大きかった。ヨーロッパもそうです。離婚して親権がなくなっても扶養する必要はあるのに、日本の現在の制度では養育費を払わないことが見逃される。強制力が弱過ぎる面があります」
親権を持つ一人の親に負担がかかりやすい日本。その原因は離婚時にあると、山口先生は解説します。
「日本における離婚の約90%は協議離婚。調停離婚が10%前後、裁判離婚は1%ほどしかありません。さらに協議離婚も、その多くが子の養育について協議をしないまま離婚に至っています。両親が協議して養育計画書を作成し、裁判所に提出する必要があるアメリカと異なり、日本では離婚届にどちらが親権者になるかを書けば、それだけで親権者を決めることができる。面会交流や養育費、財産分与などについて取り決めないまま離婚をする人が少なくありません」
制度が先か社会整備が先か。実現に向けて同時進行するしかない
日本の親権事情を“ガラパゴス”と評した山口先生。ではこれまでに、日本で共同親権の導入が検討されたことはなかったのでしょうか。ヨーロッパ諸国が「共同親権」へと移行していったのは、1989年に子どもたちの状況改善に向けた人権条約「子どもの権利条約」が、国連総会で採択されてからのこと。しかし当時、日本で議論が盛り上がることはなかったと、山口先生は振り返ります。
「子育ては母親に任せるという、性別役割分担の意識もあり、声を上げる人が少なかったのだと考えられます。しかし国境を越えて子どもを連れ去った場合、国が関与して連れ戻す『ハーグ条約』への合意を求めて、10数年前に来日した世界の首脳陣は、離婚をすると面会交流もままならなくなる状況に大変驚きました。『子どもの権利条約』に関しても、日本は1994年に批准していますが、以降、定期的に行われる審査で、離婚後に親権を持たない親との交流がないことが指摘され続けています。こういった外圧が年々激しさを増し、ようやく『共同親権』に向けて動き始めたわけです」
外圧によって変わろうとしているのも、なんとも日本的なのかもしれません。日本で離婚が多いのは、まだ子どもが幼い1歳から5歳のとき。親が離婚した未成年の子どもは、1年で約20万人にもなります。
「いきなり『共同親権』にするには危ないと主張する人もいますが、人権や平等性は普遍的なものなので、大人も子どももそこが侵害されないことが重要です。卵が先かニワトリが先かのようなもので、制度が先か社会整備が先か、足りない部分を補って一緒に進めるしかないと思います。行政や民間で、相談ができる支援体制が進むことを期待したいです」
離婚によって、どちらかの親と離ればなれになるのは子どもですが、「離婚の際、最もやってはいけないのは、どちらにつくか子どもに選ばせること」と山口先生。すなわちそれは、どちらかを捨てさせることにもなるからです。
「子どもは離婚してほしくない、けれど一緒に暮らしたいと言っても叶えられない。にもかかわらず、『あなたが決めたんだから』というのは酷すぎます。とはいえ何も知らされなければ不安になる。だから離れて暮らすけれども自由に会うこともできるし、相談もできる。親は離婚するが、あなたを変わらず愛していると伝えることが非常に重要なのです」
取材対象:山口 亮子(関西学院大学 法学部 教授)
ライター:三浦 彩
運営元:関西学院 広報部
※掲載内容は取材当時のものとなります







