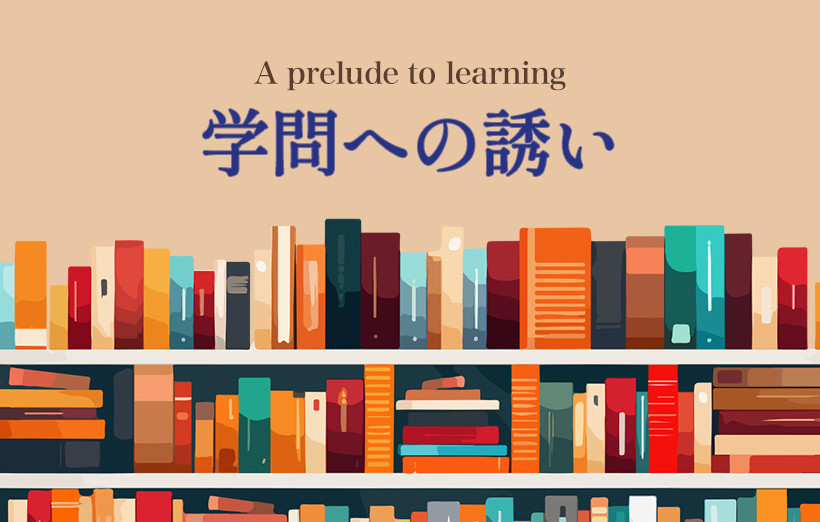イギリスの経済史からひも解く、社会に投資が根づくために必要なこと
2024年1月から新NISAが始まり、個人の資産運用としての投資が改めて注目を集めています。しかし依然として預金重視の傾向が強い日本で投資が浸透するのはこれから。
では、家計の金融資産の多くを投資が占めている欧米諸国では、どのように投資が浸透したのでしょうか。近代イギリスの経済史を研究対象とする文学部の坂本優一郎先生に、欧州に投資社会が生まれ、根付いた歴史的背景について話をお聞きしました。
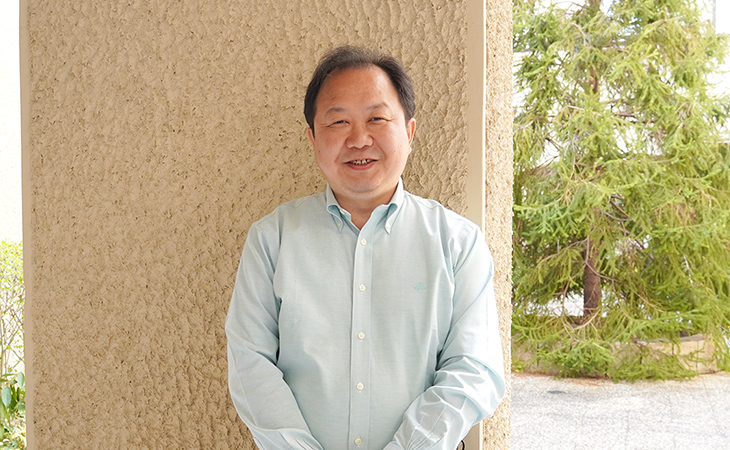
Profile
坂本 優一郎(SAKAMOTO Yuichiro)
関西学院大学文学部文化歴史学科教授。博士(文学)。大阪大学大学院修了。近世から現代にかけての西洋史研究、特にイギリス史研究を専門とする。2018年4月に関西学院大学文学部教授に着任。著書に『投資社会の勃興―財政金融革命の波及とイギリス』(名古屋大学出版会)があるほか、分担執筆での学術書多数。
この記事の要約
- 投資社会は投資先の国家の信用が基盤にあることが前提。
- 投資による資金調達が戦争の勝敗も左右した。
- イギリスでは市民に投資を浸透させるため、政府が啓蒙活動を行った。
イギリスが戦争で勝利できたのは「公債」の力
現代日本に暮らす私たちにとって投資というと、株式を思い浮かべる人も多いかもしれませんが、投資の対象となる証券には、国債・地方債といった公債もあります。坂本先生によると、世界で最初に社会に誕生したのは株式ではなく公債。12世紀中頃にイタリアの都市国家が戦費獲得のために国債を発行したのが起源とされ、株式の原型も同時期に生まれましたが、投資社会の形成に大きな役割を果たしたのは公債だと言います。
「公債は国や都市がお金を借り入れることですから、そもそも国家が人々から信用されていることが大前提。その意味で『投資社会』というのは、国家の信用を基盤に据えつつ、人々が証券の保有や売買を通じて結び付く社会、マネタリーな関係を築く仕組みを有する社会と言えます。起源は12世紀中頃と古いですが、実際に市民に投資が根付いてきたのは、ヨーロッパに近代国家が成立し始めてからです」
投資が根付くきっかけとなったのが、17世紀末から1815年まで、各国間で行われた戦争。当時、軍事技術が発達する一方で、兵器の購入や防衛設備の拡充に資金が必要となり、従来のような租税だけでは十分な戦費が調達できなくなりました。そこでイギリスを筆頭とするヨーロッパ近代国家が考え出したのが、公債による資金調達だったというのです。
「わかりやすい例を挙げると、租税から調達した戦費が100万円あったとします。その戦費を10%の金利支払い用に確保して国債を発行すれば、1000万円の戦費を調達できます。しかし国債を発行する国家に信用がなければ、つまり元本と金利の保証がなければ、国債を購入する人は現れません」
そのような状況の中、公債を巧みに活用したのがイギリスです。17世紀後半に起こった名誉革命を機にオランダと同盟を結び、証券や株式市場の仕組みを取り入れていきました。そして18世紀に入ると、いくつもの戦争を経て大英帝国と呼ばれる黄金期に至ります。
現代でも言われることですが、当時の戦争は戦費の額でほぼ勝敗が決まっていました。公債による資金調達に成功したイギリスは、対フランスをはじめとして、ヨーロッパ各国との戦いに勝利を収めることができたのです。しかしなぜ、イギリスは公債による資金調達で他国と差をつけることができたのでしょう。
「イギリスは、金利が低くても必ず投資者にリターンをすることで国家の信用を高め、投資者を集めることに成功したのです。一方、フランスやスペインでは利息を払わず元本も戻らないということが積み重なり、金利を釣り上げても投資者が集まらないという結果を招きました。このようにイギリスは投資社会を自国にうまくつくり上げたからこそ、戦争に勝つことができたと言えるでしょう」
なお、株式という仕組みが本格的に動き出したのは、17世紀にオランダで生まれた東インド会社の事業から。アジアという遠隔地とのハイリスク・ハイリターンな貿易事業において、リスクを分散するために多くの人から資金を集めて会社をつくり、その出資金の割合に応じて、貿易で得た利益を分配する株式の仕組みを導入しました。また同時期に、株式市場がアムステルダムに誕生。近代的な証券の仕組みが確立されていきました。
イギリスで投資文化の浸透にかかった期間は100年
イギリスを戦争の勝者に導いた公債への「投資」は、18世紀以降、イギリス社会に浸透していきます。ではどのように浸透していったのでしょうか。18世紀のイギリスには上流階級、中産階級、労働者階級が存在していましたが、坂本先生によると当時の投資社会の成立を牽引したのは、遊休資産(貯蓄)を持っていた中産階級だと言います。現代では新聞に株式市場欄がありますが、18世紀のヨーロッパにもすでに市場の動きを確認できる紙面が存在していたそうです。
「その頃には何万人、何十万人という投資家が各国の国債価格をチェックするような社会ができあがり、さらに18世紀後半のイギリスでは、知識人が執筆した一般向けの投資マニュアル本が出版され、大ベストセラーになっていました。こうした知識人たちが『株式はリスクが大きい。より安全なのは公債で、特にイギリス国債がおすすめだ』とか、『女性に投資をおすすめする』というようなことを記しているんです。
実際に当時のイギリスでは、女性の公債投資者が多くいました。当時は、中産階級の女性は外で働くことが、良しとされていなかった時代。だから投資で不労所得を得ることがニーズにかなっていたというわけです。親が娘の名義で公債を購入し、利息の収入だけで暮らせるようにしたり、またその娘も自分の子どもに同じことをするといった資産運用経験が、イギリスの中流階級では育まれていきました」

そして興味深いのが、18世紀後半までは投資という概念がなく、投機、つまりギャンブル的に捉えられていたということ。公債で調達した戦費によって戦争に勝ち続ける、つまり元本も利息も支払われるイギリスの状況から「イギリス公債に投資するのは、投機ではなくて投資だ」という主張をする者が現れたのです。こうして人々の中に「投資」という概念が生まれ、従来のギャンブル的な「投機」と区別されるようになったのです。
これに伴い公債保有者も増えていきます。18世紀後半には5、6万人と言われていたイギリス国債への投資者は、19世紀初頭にはロンドン近辺の住民を中心に30万人から40万人へと膨れ上がっていったといいます。しかしそれでもなかなか投資に手を出さなかったのが労働者階級。イギリス労働者階級にまで投資文化が浸透したのは、1914年に起こった第一次世界大戦のこと。つまり広く市民に浸透するまでに、100年がかかったということになります。
「第一次世界大戦が勃発し、イギリスはこれまで以上に戦費の調達を余儀なくされました。このとき政府が藁をもつかむ思いで公債購入者のターゲットにしたのが、労働者階級の人々の貯蓄です。しかし労働者階級の人々は保守的で、まだ投資を投機、いわゆるギャンブルに近いものだと考え、なかなか手を出しませんでした。少し前までの日本人の感覚に近かったのかもしれません」
しかしイギリス政府は労働者階級に向けて大々的にキャンペーンを張り、金融教育的な啓蒙活動をしていきます。さらに元本保証型の「戦時貯蓄証券」(War Savings Certificate)という名称の商品をつくり、彼らに投資を促したのです。
「これは投資信託というよりも日本の預貯金に近いような商品といえるかもしれません。イギリスにおける投資社会の動きは、 “貯蓄から投資へ”という動きを促進するいまの日本に似ている部分があるかもしれません」
経済史から見る、投資文化が浸透するために必要なこと
ここで改めて、投資社会が成立する条件を見てみましょう。坂本先生は「18世紀に限定した話で」と前置きした上で6つの条件があると言います。それは、これまで先生の説明にもあった①遊休資金の存在、②国家に信用があること、③証券の流動性を高める市場の存在、そして④投資した財産の所有権が法的に確立されていること、⑤法令遵守に関する知識、⑥投資に対する文化的な認識の変化。
④投資した財産の所有権が法的に確立されていることは、財産権が保障されていなければ、人は投資というリスクを冒せないということ、そして⑤法令遵守に関する知識にもつながります。
「⑥投資に対する文化的な認識の変化は、投機と投資の区別がされるようになったことが挙げられます。いずれにしても、歴史を研究している私の立場からすると、やはり⑥文化的な認識の変化には、時間がかかると言わざるを得ません。イギリスでは17世紀頃から長い時間をかけて成功と失敗経験を積み上げ、中流階級から労働者階級にいたるまで、投資という概念や文化を定着させるのに100年がかかりました。日本でも“貯蓄から投資へ”という流れがあります。社会背景やそれぞれの国の事情が異なるため、18世紀のイギリスの条件と比較するのは難しい部分もありますが、それでも経済史の視点から言えることは、日本で投資が定着するためには、経験や時間が足りていないということ。投資に対する文化的な認識の定着が追いついていないと考えられます」
日本で“貯蓄から投資へ”という方針が初めて打ち出されたのは、2001年6月、小泉内閣における「経済財政運営と改革の基本方針 2001」いわゆる「骨太の方針」でのこと。その後、NISAなどの施策により個人投資家が少しずつ増加しつつあります。また、2020年の学習指導要領の改訂で、2022年までに小学校・中学校・高校で金融に関する事柄を授業で教えるよう義務付け、金融庁も小学生からの啓発に力を入れるなど、変化も生まれています。
「第一次世界大戦でイギリス政府が行った労働者向けのキャンペーンのように、現代の日本政府も我々一般市民への啓発に力を入れています。こうした経験が積み重なっていくことで、一昔前の日本人が持っていた証券や投資に対するイメージが変わり、イギリスをはじめとする欧米諸国のように、投資が暮らしの中で当たり前のものとして存在する社会になる可能性は大いにあるのではないでしょうか」
取材対象:坂本 優一郎(関西学院大学 文学部文化歴史学科 教授)
ライター:蔵 麻子
運営元:関西学院 広報部
※掲載内容は取材当時のものとなります